訪問規制やMR数の減少というワードを最近よく耳にします。ただまだまだ薬の普及にはMRの存在は不可欠です。ただ中にはMRと面会しない医師もいます。
そこで今回は医師がMR以外から情報を入手する方法を考えていきたいと思います。
Contents
MRと面会しない医師はどこから情報を手に入れているのか
MRとの面会を以前よりも少し減らしている先生もここ最近増えてきています。
さらにMRとは一切面会しないという先生も一定数いらっしゃいます。
そこで「MRと面会しない先生はどのようにして薬の情報を入手しているのか」という疑問が湧きますよね。
僕も気になったので調べてみました。
MRと面会しない先生の情報の入手方法
- インターネット
- 学会
- 文献
- 他の医師から
- SNS
- 動画
- メール
- 情報誌
- 電話
有名なものからマイナーなものまでありますがMR以外ではこのくらいは情報を入手する方法があります。
インターネット
一番はインターネットだと思われます。
製薬会社のパンフレットなどの情報は基本的に製薬会社のホームページに載っています。
ですので製品について知りたい情報があれば製薬会社のホームページにアクセスすることによって知ることができます。
また薬の情報を扱うサイトも近年登場しています。そこから情報を仕入れることもできます。
学会
学会は全国から医師が集まり最新の研究結果を発表する会ですので情報の宝庫です。
MRも学会に行って勉強しますが先生も学会に行き情報を入手します。
文献
気になる内容の文献があるかどうかを調べて内容も読むことができます。
文献の情報はピンポイントで研究されているものが多いため薬のパンフレットに記載されている情報よりもより実臨床に応用できる情報が多いのが特徴です。
他の医師から
先生は他の先生とも知り合いであることが多いので先生同士で情報交換をしています。
医学部時代の同級生や先輩など知り合いは多いのでここから情報を入手する場合も多いです。
また医者同士の集まりもあると聞きますのでその時に情報交換をして情報を入手することもできると思います。
SNS
医師限定のSNSなどもあり先生同士がコニュミーションできるようなシステムもあります。
ここから情報を入手することもできます。
オピニオンドクターと呼ばれる専門医も参加していて専門の先生に直接質問できたりもします。
動画
これは動画を視聴して情報を入手するということです。
医師向けに製薬会社と連携して動画を作成している企業もありますので先生も見たい時に見れる利便性の高さから動画コンテンツは注目されています。
メール
これも動画と似ていてメールで情報を入手することができます。
情報誌
これは製薬会社が発行するパンフレットとは違って論文などからピックアップした情報を掲載しているものです。
情報誌が多くの医師に受け入れられている理由はフラットな情報が載っているという点です。
製薬会社が発行するパンフレットというのはほとんどが自社製品を中心としたものに対してこの情報誌は様々なメーカーの情報を掲載しているのでメーカーでの偏りがないフラットな情報かつ情報量が多いというメリットがあります。
電話
製薬会社には電話相談窓口があります。
薬に関しての疑問があった場合電話相談をすることができます。
自分で探すのは少し大変という方はこちらの電話相談を利用するケースがあります。
営業されるのが嫌な先生はMRには会わない
MRは営業職なので自社製品を使ってもらえるように活動します。
ですので営業されるのが嫌な先生は「MRとは会わない」という考えになるのだと思います。
また人に会うと情が入るのでそれも避けたいという場合もMRとは面会しないのかもしれません。何回も会うと自然と仲良くなってしまうのが人です。
情が入ると使いたくないのに使わなければならなくなるケースも考えられます。そうなるのが嫌という先生も中にはいらっしゃいます。
一方でピエロのように全く情がない先生もいらっしゃいますけどね。そのような先生はうまくMRを利用している気がします。
接待が規制されたのも大きい
飲食をしながらメーカーと話すことを楽しみにされていた先生が多いのも事実です。
そこで接待が規制されたことによってメーカーと先生との距離が遠くなってしまったということが考えられます。
これを狙って接待に規制をかけたので当然といえば当然ですけどね。
MR以外からも情報は入手できるが・・・
全医療機関がMRと一切面会しないとなればMR職という職業の必要性はかなり低くなると思いますがそんなことはおそらくあり得ないと思います。
なぜならば「MR以外からでも情報は入手できるがMRからも情報を入手したい」という医師は少なくないと予想できるからです。
また医師は情報を得る目的以外にもMRを必要としている場合があるのでそれは他では代用ができません。
従ってMR職がなくなることは考えにくいと思います。




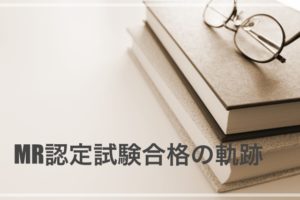












コメントを残す