Dr.が薬の選択をする際に多大な影響力を与えているのがガイドラインとエビデンスです。
今回はこのガイドラインとエビデンスがどんな影響をもたらすのかについて書いていきたいと思います。
Contents
ガイドライン
ガイドラインというのは一つの指針です。疾患を治療する上でオススメの薬剤や医学的処置が紹介されています。
ガイドラインで推奨されている薬剤や処置というのはデータが蓄積して有効と判断されたものですのでしっかりとした根拠があります。
またガイドラインで推奨されるということはその疾患のスタンダードドラッグと言えるので先生の薬剤選択へかなりの影響力があります。
また薬剤を投与する検査値の目安や外科的処置をしなければならないラインについても紹介されています。
エビデンス
エビデンスは臨床試験の結果のことです。薬というのはデータがないと実臨床では使うことができません。
そこで薬の効果や副作用などを検証するために数々のスタディが各地で行われてます。
エデビンスにはそれぞれ影響力の違いがあります。あまり影響力がないエビデンスや影響力が強いエビデンスなど様々なエビデンスがあります。
この影響力はざっくりと解説すると被験者数、試験デザイン、結果などから決まります。
またそもそも疾患を治療する必要があるのかについてもこのエビデンスが関わっています。
糖尿病を例にすると糖尿病は初期であれば大きな症状はは出ません。しかし罹患歴が長くなると徐々に症状が出る疾患です。
従ってどの程度まで血糖値をコントールすれば良いのかといったこともエビデンスに基づいて決められています。
高血圧も同様に高血圧だからといって症状が出るわけではありませんが高血圧状態が長く続くといろんな疾患に繋がっていくため適切な血圧の管理が必要になります。
従ってエビデンスというのは薬の情報提供を行う上でとても重要なことです。しっかりとした根拠がないと説得力は弱くなってしまいます。
だから薬の情報提供を行うMRもこのエビデンスについて知っておく必要があると僕は思ってます。
多大な影響力のある大規模臨床試験
エビデンスは膨大な数があるので全部を網羅するのは現実的になかなか厳しいと思います。そこで優先すべきは大規模臨床試験です。規模が大きいということはそれだけ信憑性が高いということになります。
ですので知っておいて損はないエビデンスです。知っておけば日頃の疑問を解決してくれる強い味方になると思います。
また大規模臨床試験で有効なデータが発表されれば薬の普及は加速します。それだけ信頼性もあり影響力も高いのが大規模臨床試験です。
インパクトファクター
インパクトファクターというのは引用された回数によって決まる値です。Dr.によってはこのインパクトファクターを重要視する方もいらっしゃいます。
インパククトファクターが高い論文は影響力が高いです。ですので実際にDr.に論文を提示する際にはインパクトファクターについても触れることをオススメします。
スタンダードパンフレットのデータについて
薬のスタンダードパンフレットに記載されているデータというのは製薬会社が中心となって研究されたデータです。従ってどの薬のスタンダードパンフレットにも承認時のデータは記載されています。
そしてこの承認時のデータは本当にわかりやすいです。
承認時のデータには薬の特性がしっかりと網羅されているので定期的に繰り返しアナウンスする必要があると僕は思います。
医療機関が研究したデータについて
医療機関も独自でデータの解析を行っています。それを学会で発表して薬の有用性について広めていくわけです。
このデータは製薬会社のパンフレットに載ったりもします。有効なデータであれば製薬メーカーも積極的にコールします。
中にはネガティブなデータも発表されます。これについても製薬メーカーはしっかりと説明する必要があります。
僕もネガティブなデータが出た際はしっかりと説明しています。
ネガティブなデータこそ素早く、確実に相手に説明しなければなりません。トラブルが起きてからでは遅いです。
医療機関ごとのガイドラインが存在する
これは僕がMRをやっていて気づいたことです。医療機関にはそれぞれの疾患に関する独自のガイドラインが存在します。
これは公式のガイドラインをベースにして先生の考えがプラスされたその医療機関の完全オリジナルです。しかも公式のガイドラインよりも細かくなっているケースが多い気がします。
Dr.は診療することが仕事の一つですが同時にいろんな研究をされています。だからDr.それぞれで自分の治療方針というものがありそれに基づいて診療されています。
そこでMRは先生ごとの治療方針をしっかり理解しないと有益な情報提供というのはできません。
ただMRに治療方針なんか教えたくないというDr.も中にはいらっしゃいます。聞き方次第では失礼にあたってしまうこともあります。
僕も過去に先生の治療方針を伺った際に「なんでそんなことあなたに教えなければいけないの」と言われてしまった経験があります。
その経験から治療方針を聞く理由に関して考えてみました。考えた結果相手のために治療方針を聞くという結論に辿りつきました。
従って治療方針を聞く目的が相手にきちんと伝われば失礼にはあたりません。よって治療方針の聞き方で意識することは有益な情報を提供したいというニュアンスが伝わるように会話を進めることです。
ある程度治療方針を把握していないとどのテータを提示すればいいのかがわかりませんので適度な頻度で聞いておくといいと思います。
エビデンスを駆使する
先生に情報提供する際に意識すべきことはエビデンスを駆使することです。例えばこの薬は効果が強いですとだけ伝えてもどの程度の強さであるかは伝わりません。
そこでエビデンスを一緒に紹介すれば相手にも伝わりやすくなりますし、説得力も増します。
また1日1回の服用と1日2回の服用を比べた際にも両者が飲み忘れの差がないというエビデンスがあれば1日2回の服用でも服薬回数が多いという一つのハードルをクリアできたことになります。
このようにエビデンスはかなり有効ですので多少の労力を使ってでもエビデンスについて調べる価値は高いと思います。
自分で調べた知識は忘れにくい
僕の経験からも言えますが自分で調べた論文や知識というのは忘れにくいです。
だから疑問に思ったことは論文で探すという習慣をつけておくと知識がどんどん増えていきます。
論文を探さなくても解決できそうなことは本でもいいと思います。大事なのは自分で調べることです。
論文を調べるのは最初のうちは大変ですし時間もかかります。しかし継続的にやっていけば要領を掴んできますのでそんなに苦に感じなくなります。コツコツと気長にやってみてください。
自分も統計を取ってみる
例えば副作用の発現率を伝えるためにいくつかのデータの副作用の項目だけチェックするということです。エビデンスを重ねればより説得力は増します。
再現性が高いということは実際の診療の際にも起こりうることです。どのデータにも共通していることが再現性の高い項目と言えますのでこれもやってみると仕事も幅が広がります。
まとめ
今回はエビデンスやガイドラインといった影響力の高い項目について書きました。これをうまく活用して説得力を高めていってくださいね。最後まで読んで頂きまして、ありがとうございました。ばーい。




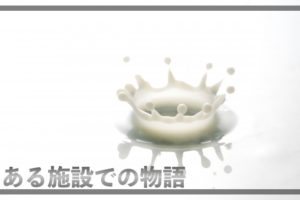

















コメントを残す