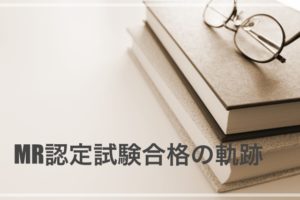最近「MR数の減少」や「MR不要論」という言葉に出会う機会があるかと思います。
そこで今回は「MR数の減少」と「MR不要論」について偏見強めの個人的な意見を書きました。
Contents
MR数が減少していることは事実
2013年度のMR数は過去最高の65752人でした。ここから少しずつ減少していき2021年度のMR数は51848人になりました。MR数は2013年度から2021年度の間で13904人の減少でした。(約20%の減少)
参考:2022年度版MR白書より
こんな感じで業界全体で見ればMR数は減少しています。ただMR数の推移は製薬会社によってかなり違います。全ての製薬会社でMR数が減少しているわけではないです。
MR不要論はなぜ唱えられたのか
次にMR不要論について書いていきます。
まずMR不要論とは「MR職は不要な職業だから将来なくなる」というなんの根拠もない理論と僕は思っております。
そして「MRができることが年々少なくなっていったこと」や「早期退職などでMR数が減少していったこと」がMR不要論を流行らせたのではないかと思います。

MR不要論の全てを否定することはできないが・・・
製薬会社によってはMR数を減らしています。しかも自然減(退職や転職)ではなく早期退職という(お金を払って辞めてもらう)少し強引なやり方を使ってです。
このことから言えることは製薬会社によっては以前よりMRの必要性が低下したということです。
かといってMR職自体がいらないというのはちょっと言い過ぎではないでしょうか。これが仮に90%減くらいならまだわかりますが・・・
▼MR職が将来なくならないことを考察した記事はこちらです
MR数が減少した理由を考えてみる
このテーマを扱うのであれば製薬会社別に考察するのが正しいやり方だと思います。なぜならば製薬会社によって状況が違うからです。
しかし全ての製薬会社のMR数の推移を追うことが僕にはできないので一般論になってしまうことは予めご了承頂ければ幸いです。
MR数が減った理由として考えられること
- 新薬が出にくくなった
- 開発する薬がスペシャリティ領域へ移行している
- 利益の確保が難しくなった
- 面会できなくなった施設が増えた
- 今後を見据えて人員削減
新薬が出にくくなった
以前に比べて新薬が出にくくなったということがMR数にも影響していると思います。というのもMRが一番必要になる時は新薬が発売した時だからです。
従って以前に比べて新薬が出なくなったのでMR必要性が下がったということが考えられます。
開発する薬がスペシャリティ領域へ移行している
大手製薬会社を中心に以前は生活習慣病関連の薬が数多く開発されていました。しかし生活習慣病関連の薬はある程度開発し終えたので大手製薬会社を中心にスペシャリティ領域へ徐々に移行しています。
生活習慣病の薬を主に処方するのは内科の開業医の先生です。(もちろん病院でも処方されます)
また生活習慣病の薬は似たような薬が多く差別化が難しいので情報提供で売っていくというよりは面会頻度や関係性(付き合い関係)で売っていくのが主流です。
ということはMR数が必要になります。
それに比べてスペシャリティ領域の薬は開業医よりは病院で主に処方されます(専門の開業医で処方される場合もあります)
開業医の数に比べて病院の数は少ないのでMRの数もそこまでいりません。
またスペシャリティ領域の薬は面会頻度や関係性で勝負するよりは製品力や情報提供の質で勝負するのが一般的です。
ということは面会頻度もそこまで高くないのでMR数も以前より少なくても問題ありません。
従って開発領域の変化がMR数に影響を及ぼしているのはではないかと思います。
利益の確保が難しくなった
製薬会社が利益を確保できなければ従業員であるMRを雇うことができません。薬価改定や特許切れに加えて新薬が今までのように爆発的に売れない状況ですので製薬会社は利益を確保することが以前よりもできなくなっています。
従ってMR数の最適化を行ったということが考えられます。
面会できなくなった施設が増えた
MRと面会しない医療機関(以前の頻度では面会しない)が増えた可能性があります。(以前からMRと面会しない先生もいます)
この理由にはMR活動が制限された(情報提供の規約も厳しくなりました)こととスポンサー業務(接待等)がかなり制限されてしまったことに加えてインターネットやSNSなどの普及が考えられます。
医療機関側のMRのニーズは情報提供以外にも結構あるのでそれが制限されてしまうと面会がしにくくなります。
またMR以外から情報を得る手段(インターネットやSNSなど)も以前に比べて増えたのでMRと面会する頻度が減った先生が増えた可能性もあります。
面会がしにくくなる(面会頻度が減るもしくはMRと面会しない先生が増える)ということはMRの数に影響を及ぼすことになります。
今後を見据えて人員削減
今の状況を考えると新薬の開発は今後ますます大変になっていくことが予想されます。また利益の確保も今後ますます大変になっていくことが予想されます。
従って今後を見据えて余裕のあるうちに人員削減を実施していることもMR数の減少理由の一つではないでしょうか。
MRがいらないケース
製薬会社にとってMRは自社製品を宣伝する存在なのでやはり必要です。ただ医療機関側にとってMRは必要でないケースがあります。
そこで必要でないケースの具体例をあげると以下の通りです。
- 効果が良くないのにPR
- 相手の妨害
効果が良くないのにPR
明らかに自社製品が他社製品の下位互換なのにその製品をPRして採用や増量を目指す行為はただ相手に害を与えているだけです。
会社としては売り上げを伸ばすためにこのようなことをやるわけですが医療機関側にとっては得るものはありません。
むしろ治療の邪魔をしているだけです。
相手を妨害
MRは競合品の採用が決まりそうな時に掻き回すことでそれを妨害するようなことも営業の一貫としてやります。
結局のところ相手の利益よりも自分の利益を優先するわけです。
また後発品に変えた方が国にとっても薬局にとってもメリットがあるのにそれを妨害して先発品を使って欲しいとお願いするのは医療機関にとっては迷惑行為になります。
MR不要論は過剰すぎる
様々な理由でMRの必要性が以前よりも減っているということを否定することは難しいと思います。実際にMR数を減らした製薬会社も多々あります。
しかしながらMR職が将来なくなるということは言い過ぎだと思います。
なぜこんなにも「MR職は不要だからなくなる」と言われているのでしょうか??僕はすごく疑問に思います。皆さんはどう思いますでしょうか??